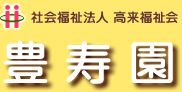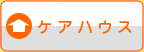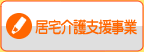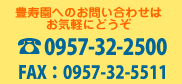部屋の間取り・設備は?
全室個室となっており、洗面・ミニキッチン・ナースコール・冷暖房・トイレ完備です。
(一人部屋7畳半・板の間、夫婦部屋6畳2間)
入居料金はどの程度ですか?
入居される方の前年度の所得により異なりますが、年収150万円以下の方で、1ヶ月7万円前後になります。対象収入によって14階層に別れます。(利用料金表参照)
【参考】
- 対象収入とは、前年の収入から必要経費を差し引いた金額
(税金・健康保険料・介護保険料等) - 入居料金の内訳
- ご夫婦の場合、ご夫婦の収入合計額を2で割った金額がおひとりの対象収入です。階層によって控除があります。(1階層のみ事務費30%)
- おひとりで夫婦部屋入居の場合、管理費のみを2倍いただきます。
- ご本人の収入が入居料に満たない場合、ご親族の援助があれば入居可能です。
(ご本人の年金が少ない方、生活保護を受けている方も入居可能) - だいたいの収入がわかれば、利用料金表にて階層の目安をご覧下さい。
敷金(入居一時金)はいくらですか?
いただいておりません。退去される時に、畳代・居室の改装代を実費でお願いしております。(5〜10万円程)
入居対象者は?
60歳以上で身体機能の低下や家庭環境などの理由で自宅生活に不安な方、または困難な方。ご夫婦の場合のいずれか一方が60歳以上であれば入居可能です。身元引受人が立てられる方。日常生活に問題行動がない方(痴呆不可)。車椅子でも入居可能です。
自力で食事、排泄が可能であれば入居できます。(要介護3程度まで)
入居する際に必要な書類は?
利用申込書・身元保証書・健康診断書・収入申告書(所得証明書等)・住民票・入居契約書・確約書(親族負担のある方)
施設見学はできますか?
随時、行っております。お車をお持ちでなければ、お迎えにあがります。お気軽にお越し下さい。(土日祭日でも可能)
体験入居はできますか?
寝具類など準備しておりますので、2、3日滞在してみてはいかがでしょうか?送迎もいたします。(利用料日額4,200円)
入院時は退去になるのですか?
いいえ。長期入院に至った場合(3ヶ月を目処)に状況次第で退去される場合もあります。
(参考:2週間以上入院の場合、食費相当額として1日750円返金いたします。)
寝たきりになった場合、退去しなければいけませんか?
在宅サービス(ディ・ホームヘルパー)等の利用ができますので、ある程度の介護が必要であっても入居は可能です。かかりつけ医の往診も有ります。しかし、医療面等でどうしても居室の生活が困難になった場合は退去されることもあります。
(参考:長期入院後退去される場合、他施設への紹介もいたしております。(特養・老健などがありますが基本的に医師の判断・ご家族の意向を尊重いたします))
市街地より離れているので生活に不便ではありませんか?
スーパーなどへの買い物バスの運行(週1回)など<、通院の送迎サービスなどを行っておりますので、特に不便ではありません。(その他、銀行・クリーニング店の来園、切手の販売、宅配便の取り次ぎなどがあります)
手術をして健康に不安があるのですが・・・(持病があり通院している)
心配いりません。地元の病院との緊密な連絡体制があり、緊急の場合でも迅速な対応が可能です。(夜間は宿直者が1名、各居室にナースコールの設置、看護師在職)
(参考:かかりつけ病院への紹介状を提出していただき、定期受診が可能です。(ペースメーカー使用者でも入居可能))
外出・外泊は自由ですか?
届けを出していただければ自由です。食事の準備等がありますので、早めに御連絡ください。門限は午後8時となっております。(連絡があれば、午後8時以降でも可能)
(参考:ご家族の方も施設に宿泊できます)
入居に際し持参するものは何が必要でしょうか?
日常生活に必要なもの、寝具類・テレビ・テーブル・タンス・冷蔵庫・ベッド等
駐車場はありますか?
ございます。駐車料金はいただいておりません。
食事・入浴について
食事:朝8時・昼12時・夜6時(冬5時30分)に栄養士による高齢者に適したメニューを提供いたします。
入浴:隔口以上準備(夕方5時〜8時)、シャワーは毎日利用できます。(昼間)
介護が必要な場合、ヘルパーによる昼間入浴(機械浴有り)
健康・相談について
暮らしや健康面での相談・助言が気軽に受けられます。(各種専門職が応対します)定期受診・年1回の健康診断等により、病気の早期発見・早期治療に努めております。
趣味・娯楽について
季節感のある年間行事の他に、書道・生け花・詩吟・カラオケ・バスハイク(年数回)等、地元小・中学校、保育園から慰問の受け入れなど、地域との交流を推進しております。